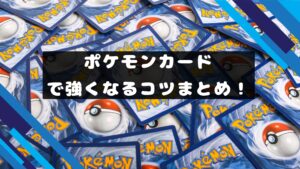ポケモンカードを始めたばかりで、「どうやってデッキを作ればいいの?」と悩んでいませんか?本記事では、ポケモン カード 初心者の方に向けて、誰でも理解しやすいおすすめのデッキ作り方コツを丁寧に解説していきます。はじめての方でも安心してバトルを楽しめるよう、ルールの基本から、カードの枚数配分、構築済みデッキの活用方法、さらには最強を目指すための応用的なデッキ調整法まで幅広く紹介しています。
デッキ作りが初めての方も、この記事を読めば自分だけのデッキを組む第一歩を踏み出せるはずです。今後のプレイをより楽しむためのヒントが詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
- デッキを作る際に軸となる考え方
- 初心者に適したカードタイプの選び方
- バランスの良い枚数配分と構築方法
- 勝率を上げるための調整や改造のコツ
ポケモンカード初心者におすすめするデッキ作り方の基本

デッキ作り方コツはまず軸を決めること
最初に意識すべきコツは、「デッキの軸となるポケモンや戦い方」を明確にすることです。どんなに強いカードを持っていても、全体の方向性が定まっていなければ、効果的に戦うことはできません。
軸を決めることで、デッキ内のカード選びが一気にスムーズになります。例えば「特定のポケモンの強力なワザを活かしたい」「序盤から素早く攻撃を仕掛けたい」など、戦い方のイメージができれば、それに必要なサポートカードやエネルギーの配分も自然と決まってきます。
例えば、ゲンガーのような高火力型ポケモンを主役にしたい場合、「進化前のたねポケモン」「必要なエネルギー」「ドローサポート」などを中心にカードを組み立てる必要があります。このように、主役ポケモンを軸にデッキ全体のバランスを取ることが重要です。
逆に、軸が定まらないまま好きなカードを詰め込んでしまうと、カードの役割が重複したり、逆に必要なカードが足りなかったりすることが多くなります。その結果、手札事故やエネルギー不足が起こりやすく、思うようにバトルを進められません。
だからこそ、最初は「好きなポケモン」「使いたいワザ」「目指す戦い方」のどれか一つに注目し、それを中心に構築してみるとよいでしょう。
初心者におすすめのカードタイプとは

ポケカ初心者にとって、デッキを作る際に扱いやすいカードタイプを選ぶことはとても大切です。最初のうちは、扱いやすさとカードの入手しやすさを重視したタイプを選ぶとよいでしょう。
特におすすめなのが「草タイプ」「炎タイプ」「雷タイプ」のいずれかです。これらのタイプは構築済みデッキが多く販売されており、必要なエネルギーやサポートカードを揃えやすいというメリットがあります。また、比較的シンプルな戦術で戦えるため、複雑なコンボやタイミングに頼らずプレイしやすい点も魅力です。
例えば、炎タイプのデッキは「高火力で相手を早く倒す」スタイルが多く、試合展開が分かりやすいため、初心者にとって理解しやすい戦い方ができます。一方、雷タイプはスピード重視でエネルギー加速に優れるカードが多く、試合をリードしやすいのが特徴です。
ただし、どのタイプにも弱点があり、相手のタイプによっては不利になることもあります。これを理解しておくことで、バトル中に予期せぬ展開が起きても落ち着いて対処できるようになります。
このように、扱いやすくて強みが分かりやすいタイプを選ぶことで、デッキ構築やバトルの基本を自然と学べるようになります。初めの一歩としては最適な選択肢と言えるでしょう。
デッキの枚数配分はどうする?
デッキを作るときは、カードの種類ごとに適切な枚数配分を意識することが重要です。ポケモンカードのデッキは60枚ちょうどで構成する必要があるため、バランスが崩れるとバトルが不安定になりやすくなります。
一般的なおすすめ配分は、以下の通りです。
- ポケモン:15~20枚
- エネルギー:13~15枚
- トレーナーズ:25~30枚
このような構成にすると、ポケモンを引ける確率、ワザを使うためのエネルギーを確保する確率、手札や場を整えるためのトレーナーズを使える確率のバランスが良くなります。
例えば、攻撃力の高いポケモンを多めに入れても、エネルギーが不足していてはワザを出せません。また、ポケモンを場に出す手段がなければ序盤で不利になる恐れがあります。だからこそ、各カードの役割に合わせて適切な比率を考える必要があります。
ただし、デッキの軸や戦い方によって配分は変化します。エネルギー加速が得意なデッキではエネルギー枚数を減らしても問題ない場合もありますし、逆に戦略的に多めのトレーナーズを採用する構築もあります。
まずは基本の配分で組んでみて、実際に回しながら調整していくことが上達への近道です。
ポケモン カードのルールを理解しよう
ポケモンカードでバトルを楽しむためには、基本的なルールをしっかり理解しておくことが大切です。ルールを把握していないと、せっかくデッキを作っても実際の対戦で困ってしまいます。
ポケモンカードのバトルは、1対1の形式で行います。お互いに60枚のデッキを使い、6枚のサイドカードを取りきるか、相手のポケモンをすべて倒して勝利を目指します。場にはアクティブポケモン(バトルポケモン)1匹と、ベンチに最大5匹のポケモンを出すことができます。
ターンの流れは、主に「山札からカードを1枚引く → ポケモンを出す → エネルギーを1枚つける → ワザを使う」といった順で進みます。トレーナーズやグッズ、サポートカードを適切なタイミングで使いながら、バトルを有利に進めていくのがポイントです。
また、ポケモンごとに「たねポケモン」「進化ポケモン」といった段階があり、進化させることでより強力なワザを使えるようになります。ただし、進化は場に出してから次のターン以降にしか行えません。
特に初心者のうちは、サイドカードの仕組みや、1ターンに使えるカードの種類(サポートは1枚まで、グッズは何枚でも可)など、細かい部分で混乱することもあります。慣れないうちは公式のチュートリアルや構築済みデッキで練習するのがおすすめです。
基本的なルールを押さえておくことで、デッキ作りもバトルもスムーズになります。
まずは構築済みデッキを活用しよう
ポケモンカードを始めたばかりの方は、まず構築済みデッキを使ってみるのが非常におすすめです。これは、あらかじめ60枚で完成された状態のデッキのことで、買ってすぐに遊ぶことができる点が大きな魅力です。
構築済みデッキには、初心者でも扱いやすいカードがバランス良く組み込まれています。エネルギー、ポケモン、トレーナーズカードの比率も整っているため、いきなり自分で一から作るよりもスムーズにゲームの流れを覚えることができます。
例えば、「スターターセットex」などは、ニャオハ・ホゲータ・クワッスといった人気ポケモンが中心になっており、それぞれのデッキにはポケモンexという強力なカードも1枚ずつ収録されています。初心者が実際のバトルを体験しながら、カードの使い方や役割を学べるように工夫されているのが特徴です。

一方で、構築済みデッキはあくまで入門用に設計されているため、大会レベルの強さを求めると物足りなさを感じることもあります。また、同じ構築済みデッキを持っている人とは内容が完全に同じになるため、プレイの幅が狭くなる可能性もあるでしょう。
それでも、ルールやデッキの仕組みを覚えるためには、構築済みデッキを活用するのが最適な方法です。慣れてきたら、少しずつカードを入れ替えて、自分なりの戦術を加えていくとより楽しめるようになります。
ポケモンカード初心者におすすめ!デッキの作り方応用編

最強を目指すならデッキ調整がカギ
強いデッキを目指すうえで欠かせないのが、実際に使いながら何度もデッキを調整することです。どんなに良いカードが入っていても、試合の流れに合っていなければ真価を発揮することはできません。
調整とは、デッキを回してみて感じた「引きにくさ」「手札事故」「決め手の不足」などを洗い出し、カードの枚数や種類を見直す作業を指します。例えば、エネルギーが序盤に来すぎるようであれば枚数を1〜2枚減らし、ドローソース(手札を増やすカード)を増やすといった調整が効果的です。
たとえば、レントラーを主軸にしたデッキで手札が細くなりやすいと感じた場合、安定したドロー能力を持つ「ビーダル」を1〜2枚加えると状況が大きく変わることがあります。このように、一枚一枚の役割と必要性を見極めながら調整していくことが、最強への第一歩となります。
ただし、やみくもにカードを入れ替えると逆効果になることもあるため、調整は一度に少しずつ行うのが基本です。毎回バトルの結果を記録し、変更した部分がどのように影響を与えたのかを確認する習慣をつけると、より完成度の高いデッキに近づけます。
環境に合わせたデッキの改造方法
勝率を上げたいなら、今の対戦環境に合ったデッキ構築が必要不可欠です。対戦で多く使われているデッキタイプや戦術を把握し、それに対応できるように自分のデッキを調整することを「環境対応」と呼びます。
このとき重要なのは、「どのデッキに強くしたいか」を明確にすることです。例えば、現環境でボムリザやドラパルトexが流行しているのであれば、それらに不利にならないよう対策カードを加えると良いでしょう。具体的には、相手の特性を封じるカードや、ベンチ狙いの攻撃に備える「マナフィ」のような守りのカードが有効です。
また、対戦相手がよく使うであろうサポートカードやグッズの傾向を予測し、自分のカードのタイミングを調整することで、相手の戦術を崩すことも可能です。例えば、「ボスの指令」を減らして「カウンターキャッチャー」を増やすような変更は、終盤の勝負で効く場合があります。
一方で、対策カードを入れすぎると本来のデッキコンセプトが崩れてしまうこともあります。環境意識は大切ですが、自分のデッキがやりたい動きを確実にできるかも忘れてはいけません。
このように、環境を読んだ改造は、相手に合わせつつも、自分の軸はぶらさずに調整するのが理想的です。定期的に大会結果や流行デッキを確認する習慣をつけると、自然と改造の判断ができるようになります。
よく使われるトレーナーズカード例
デッキを安定して動かすために、トレーナーズカードは非常に重要な役割を果たします。中でもよく使われている定番のカードを知っておくことで、初心者でもデッキの完成度を一気に高めることができます。
まず注目したいのが、「博士の研究」です。手札をすべてトラッシュして7枚引くという強力な効果があり、状況を一気に打開できます。手札を揃え直したいときや、引きに行きたいカードがあるときに便利です。
次に、「ハイパーボール」も非常に汎用性が高いカードです。手札を2枚トラッシュすることで、好きなポケモンを1枚山札から持ってこられるため、バトル序盤でも終盤でも活躍します。必要なポケモンを早く場に出せるかどうかは、勝敗に直結するポイントです。
また、「ネモ」や「ナンジャモ」といったサポートカードも人気があります。それぞれ引ける枚数や効果は異なりますが、手札を整える動きを助けてくれるため、複数枚の採用がよく見られます。
ただし、トレーナーズカードは便利な反面、入れすぎるとポケモンやエネルギーが不足する原因にもなります。基本的には25~30枚前後が目安ですが、自分の戦い方に合わせて種類と枚数を調整することが大切です。
おすすめのスリーブと保管方法
カードの寿命を守るためには、スリーブでの保護と適切な保管が欠かせません。特にポケカはプレイ中にシャッフルを繰り返すため、カードの角や表面が傷つきやすくなります。
スリーブにはいくつか種類がありますが、ポケモンカード公式の「デッキシールド」や、硬めの外部メーカー製スリーブが初心者にも扱いやすくおすすめです。まずは、カードにぴったり合う「インナースリーブ」を1枚目に使用し、その上からデザイン入りスリーブ、さらに外側に透明スリーブを重ねることで、三重保護が可能です。
とはいえ、三重スリーブにすると厚みが出てシャッフルがしづらくなるというデメリットもあります。そのため、扱いやすさを重視するなら、二重スリーブでも十分な保護力があります。
保管方法については、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保存するのが基本です。カードをまとめて収納できる「カードケース」や「ストレージボックス」を使うと、種類別に整理しやすく便利です。また、大会などに出る予定がある方は、使用するスリーブに擦れや汚れがないかを事前に確認し、予備を持っておくことも忘れないようにしましょう。
こうした管理をしっかり行うことで、大切なカードを長くきれいな状態で保つことができます。
デッキレシピはネットで探して参考に
効率よく強いデッキを組みたいなら、ネット上にあるデッキレシピを活用するのがとても効果的です。初心者にとっては、完成されたレシピを見て学ぶことで、自分でデッキを作る際の基準や構成の考え方を理解しやすくなります。
多くのプレイヤーは、大会で使用したデッキや新カードを取り入れた構築例を、X(旧Twitter)やYouTube、トレーディングカード専門のサイトに投稿しています。特にYouTubeでは、実際の対戦映像や一人回しの様子も見ることができるため、カードの使い方や流れをより具体的にイメージできます。
例えば、「博士の研究」や「ハイパーボール」のような定番カードの使われ方や、環境に合わせたカードの採用理由など、細かな工夫が見える点は非常に参考になります。そのまま真似するのではなく、自分が持っているカードや好きなポケモンに合わせて調整することで、オリジナル性も持たせやすくなります。
ただし、ネットの情報は古いものも多いため、日付や投稿者の意図を確認することが大切です。また、公式大会で使用できないカードが含まれている場合もあるので、レギュレーションにも注意しましょう。
こうした点に気をつければ、ネットのデッキレシピは初心者にとって強力な学習ツールになります。まずは複数のレシピを見比べ、共通点や違いに注目するところから始めると良いでしょう。
ポケモン カード 初心者 おすすめ デッキ 作り方のポイントまとめ
- デッキ構築では軸となるポケモンや戦術を最初に決める
- 扱いやすさと入手性から草・炎・雷タイプが初心者向き
- デッキはポケモン・エネルギー・トレーナーズの比率を意識して配分する
- バトルの基本ルールやターンの流れを理解しておく
- 構築済みデッキを使うことでルールとカードの使い方が学べる
- 実戦を通じてデッキのバランスを調整し続けることが重要
- 環境に応じた対策カードの導入が勝率アップにつながる
- 汎用性の高いトレーナーズカードを取り入れると安定しやすい
- スリーブや保管方法に気を配りカードの劣化を防ぐ
- ネット上のデッキレシピを参考に構成や戦術を学ぶ